今回は、現在(2019.01.25)、高2、高1の皆様へ向けてのお話です。
理科は基礎を取るのがオススメです。
(センター受験に「**基礎」は2科目で100点分、物理・化学・生物・地学から2つ選ぶ形)
基本的な部分をしっかり学校の授業で覚えておけば8割以上を取るのは難しくない、、、と思ってます。
化学基礎 第一問
「元素のお話」でした。
問1
問2、問3
モル計算ができる+%計算できる、は理科では最低条件だと思います。
問4
問5、問6
電子式が書けないとちょっと難しい。
問7
「ベーキングパウダー=重曹=炭酸水素ナトリウム」はマメ知識として知っておいて良いと思います(笑)
最後、塩化カルシウムか炭酸カルシウムの2択にしたのは、、、
aで炭酸水素ナトリウム(ということは炭酸ナトリウムと迷わせるつもり)
bはバリウム
cで残ったのが、この2つ、という考え方。あとは、どっちが中性になるか、考えればイケるはずですね。
化学基礎 第二問
「論理的に、1つずつ」
問1
「正しい・誤り」の問題はセンターでよくある。
「含まれている単語が間違ってる」「文章が(論理的に)間違っている」というのがどの教科にもよくある形で、それに「計算しないとわからない」が加わっているのが理科によくある形。
計算自体は「モル計算」だが、「気体が同じ体積」=「同じmol数」、「物質のmol数とその物質を作る原子のmol数の関係」、といったmolに関する基礎的(〜少し発展的)な知識が無いと解くのは難しいかも。
問2
最近高校入試でもありがちな「実験っぽいもの」「グラフから読み取れるもの」パターン。
発生する水素は無限に増えていかない→「何かが全部反応し終わる点がある」ことがわかると、超簡単。
V2・V1で反応はそれ以上増えない→「亜鉛が全部反応してしまう量がV2・V1である」だけ。
反応式が書けて、比例計算できれば問題なし。
問3、問4
問4の答え→4
問4が一番難しい(面倒くさい)と思います。中和についての知識+計算方法が使える、ようになっていないとキビシイ。
問5、問6
問6、酸化還元・酸化数のルール、計算はできるようにしておくべし。
全体通して
第二問が苦しくなく解けるようにしましょう。特に問1、問4、が勝負かな、、、と思います。
出来ない問題を覚えるのではなく「計算方法」であったり「解くために必要な事柄」をしっかり覚えることが重要です。
センターは知識が無くても「論理的に考える」ことで解ける問題がよく出題されています。理科の基礎はそれが多いように感じています。「しっかり考えて1つずつ階段をのぼるように解く」ことで、正解にたどり着ける問題ばかり、、、でも無いんですけどね(笑)
まずは、知識を身につけて、その上で「論理的に解く」を身につけましょう。
入塾・家庭教師に関して
面談+無料体験授業からのスタートです!
大学入試対策、、、してないわけじゃないんですよ、実は。
保護者の方からの、センター入試や大学受験全般・進路相談も受け付けています(1.5時間〜塾で個別面談しております)。
その他、個別のお問い合わせも以下からお願いします。
- お問い合わせ(メールフォーム)
- LINE@「札幌の家庭教師屋さん」
 (←でLINE登録できます)
(←でLINE登録できます) - お電話 050−5318−8393
よりご連絡ください。よろしくお願いします。
札幌の塾BASEホームページ
札幌の家庭教師屋さんホームページ も御覧ください。m(_ _)m










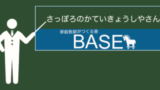
コメント